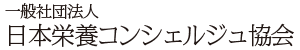アスリートのパフォーマンスを変える「隠れた身体データ」活用法 ─ 見逃せない6つの科学的知見
近年、アスリートの指導現場では個別のバイオマーカーを活用した科学的アプローチが主流となっています。
従来の「一つの数値だけを見る」方法から、複数のマーカーを組み合わせた「パネル評価」へとシフトすることで、身体コンディションの全体像をより正確に把握できるようになりました。
炎症、筋肉ダメージ、栄養状態など多面的なデータを統合することで、トレーニングや休息のタイミングをデータドリブンで決定し、クライアントのパフォーマンス向上を実現できます。
日本栄養コンシェルジュ協会noteの記事では、注目すべきバイオマーカーについて、運動指導者向けに解説しています。
本記事で概略を押さえた後に、ぜひnoteの記事をご一読ください。
T:C比とCK値が示す「オーバートレーニング」の兆候
テストステロンとコルチゾールの比率(T:C比)は、アスリートの回復状態を評価する重要な指標です。
T:C比が30%以上の低下、または0.35×10⁻³未満になるとオーバートレーニングのリスクが高まり、筋分解やパフォーマンス低下につながります。
また、クレアチンキナーゼ(CK)は筋肉損傷の度合いを示すマーカーですが、アスリートでは通常より高値になりやすいため、オフシーズンの「個別ベースライン」を設定することが推奨されます。
これらを継続的にモニタリングすることで、負担と回復のバランスを最適化できます。
見逃しやすい「機能的鉄欠乏」への対策
たとえ貧血と診断されていなくても、機能的な鉄欠乏によって持久力や集中力が大きく損なわれることがあります。
特に女性アスリートや持久系競技者は注意が必要です。
フェリチン35μg/L未満、ヘモグロビン11.5g/dL未満、トランスフェリン飽和度16%未満が目安となります。
ヘモグロビンのみの検査では見逃しやすいため、複数の指標を併せて確認し、専門家による栄養指導を受けることが重要です。
水分管理とデータ活用で防ぐパフォーマンス低下
「喉が渇いた」と感じた時点で、すでに脱水が進行している可能性があります。
急激な体重減少が2%以上、尿色が4以上、尿比重が1.020以上、血漿浸透圧が295 mOsm/kg以上などの客観的指標を日々チェックすることで、感覚だけに頼らない計画的な水分補給が可能になります。
「個別ベースライン」設定の重要性
一般的な基準範囲は活動量の低い集団をもとにしているため、アスリートには適用できないケースが多々あります。
シーズンオフや体調良好時に複数回測定し、自分専用のベースラインを設定しましょう。
そこからの変化をチェックすることで、オーバートレーニングや回復不足の兆候を高い感度で察知できます。
全文はこちらからご覧いただけます。
アスリートも驚愕!パフォーマンスを劇的に伸ばす6つの科学的真実【隠れた身体データ活用ガイド】
日本栄養コンシェルジュ協会note記事では、パフォーマンス向上のための栄養戦略ベスト5やオーバートレーニングの栄養的サインも掲載しております。
ぜひ、スポーツ選手の指導のためのヒントとしてお役立てくださいませ。