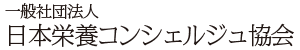クライアントの睡眠不足が招く代謝リスクと運動指導への影響│最新研究から読み解く改善アプローチ
運動指導の現場で、「最近疲れが取れない」「体重が落ちにくい」というクライアントの声を耳にすることはありませんか?
実は、その背景には慢性的な睡眠不足が潜んでいる可能性があります。
成人には7〜9時間の睡眠が推奨されていますが、現代社会では仕事や育児などで睡眠の優先順位が下がりがちです。
近年の科学的研究により、睡眠不足が代謝機能や概日リズムに深刻な影響を及ぼすことが明らかになっています。
日本栄養コンシェルジュ協会noteの記事では、睡眠不足がもたらす悪影響を、運動指導者向けに解説しています。
本記事で概略を押さえた後に、ぜひnoteの記事をご一読ください。
睡眠不足が引き起こすホルモンバランスの崩れ
睡眠不足が続くと、体内では食欲・代謝調節に関わるホルモンバランスが大きく乱れます。
具体的には、食欲を抑制するレプチンが減少する一方で、コルチゾールや成長ホルモン放出ペプチドが増加し、空腹感が強まります。
その結果、クライアントは高カロリー食品を選びやすくなり、肥満や糖代謝異常のリスクが高まります。
さらに睡眠不足は高血圧、糖尿病、脳卒中といった生活習慣病との関連も指摘されています。
不眠症・睡眠時無呼吸症候群のリスク
不眠症の有病率は専門家面接では12.4%、自己申告調査では16.3%と推計されています。
そして、若年成人では22.6%が入眠困難を経験しています。
また、アレルギー性鼻炎を持つ方は閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)のリスクが2.4倍高まることも確認されています。
これらの睡眠障害は心血管疾患、うつ病、慢性疼痛などのリスクを増大させ、日中のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。
食事の質(HEIスコア)と睡眠の深い関係
興味深いことに、食生活の質を示すHEI(Healthy Eating Index)スコアが高い人ほど、睡眠の質が良くなり、異常な睡眠時間となるリスクも低下することが研究で示されています。
野菜・果物・全粒穀物・良質なたんぱく質源をバランス良く摂取する食習慣が、睡眠リズムや深い眠りを得やすくすることが科学的に証明されているのです。
運動指導と合わせて栄養面からのアドバイスが、クライアントの睡眠改善に直結します。
デジタル睡眠介入とCBT-iの可能性
最新の研究では、スマートフォンやパソコンを活用したデジタル睡眠介入、特にCBT-i(認知行動療法による不眠治療)が大きな効果を示しています。
大学生や若年成人への介入研究では、不眠症の重症度がHedges g=−4.08という大規模な改善効果が確認され、睡眠効率もHedges g=0.62と有意に向上しました。
運動指導者として、クライアントにこうした最新のアプローチを提案できる知識が求められています。
全文はこちらからご覧いただけます。
睡眠不足が引き起こす代謝リスクとその具体的改善策を徹底解説|質の高い睡眠で健康を守ろう
日本栄養コンシェルジュ協会note記事では、睡眠の質が美容与える影響や代謝を整える食生活についても掲載しております。
ぜひ、クライアントの睡眠不足解決のヒントとしてお役立てくださいませ。